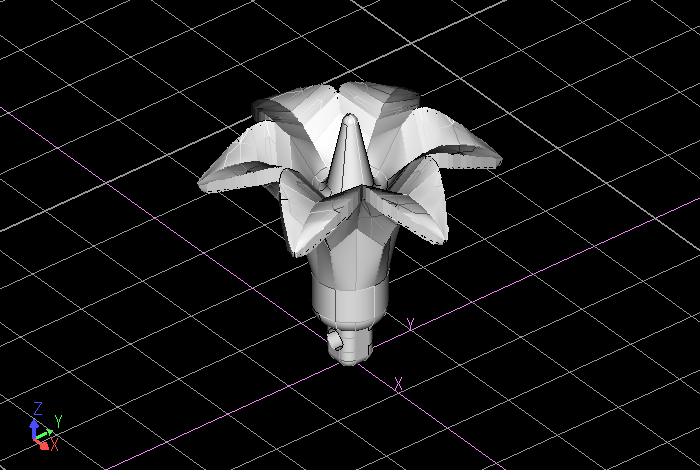
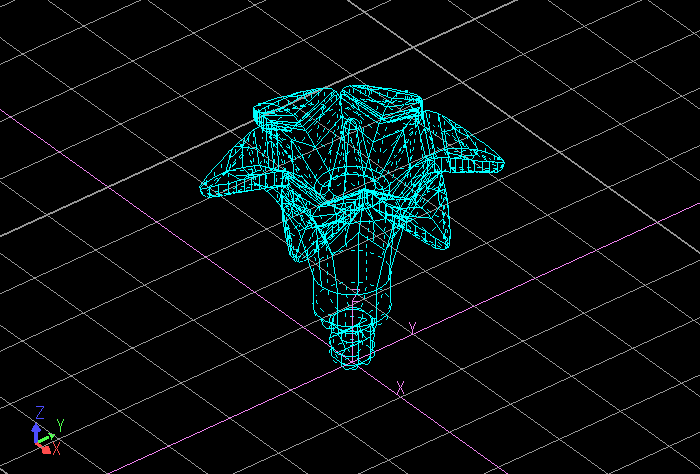
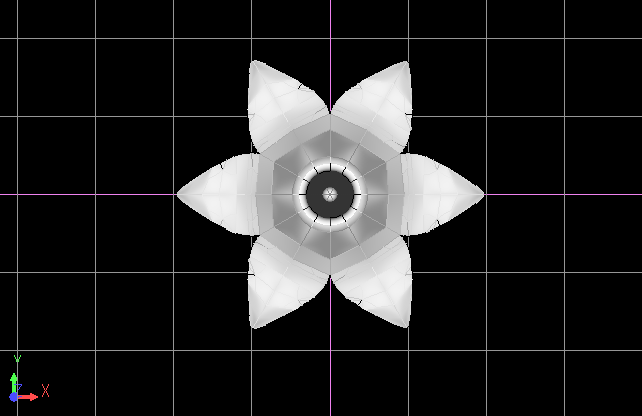
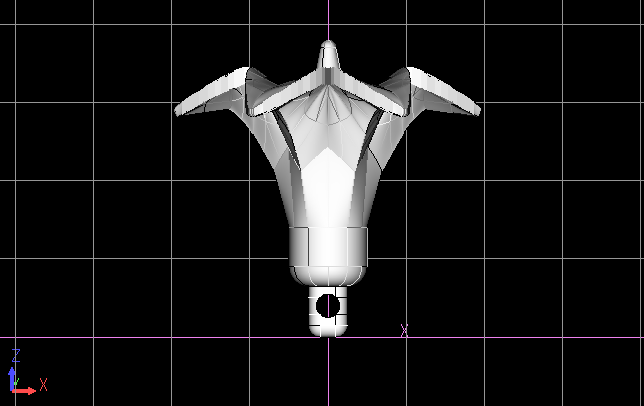
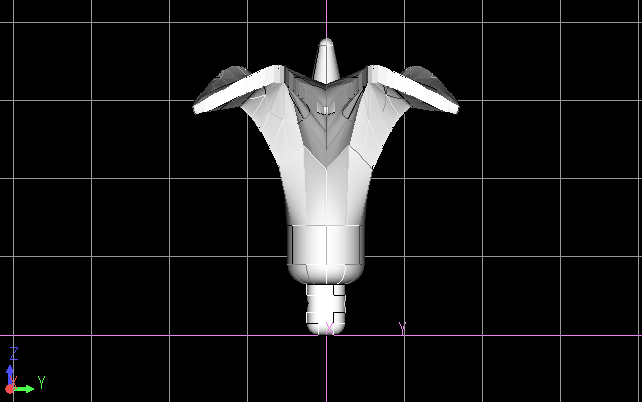
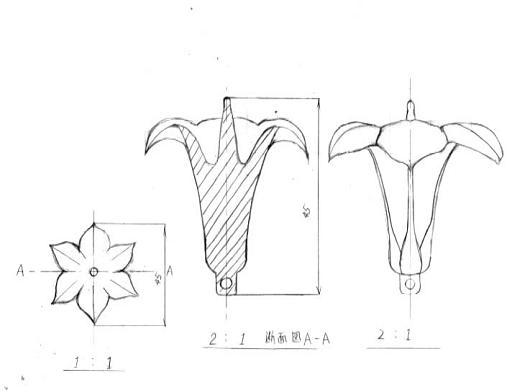
| 旋盤,ノコ盤を用いた材料の形出し |
| ↓↓ |
| 3次元切削機を用いたユリ下部の切削 |
| ↓↓ |
| 3次元切削機を用いたユリ上部の切削 |
| ↓↓ |
| 完成 |
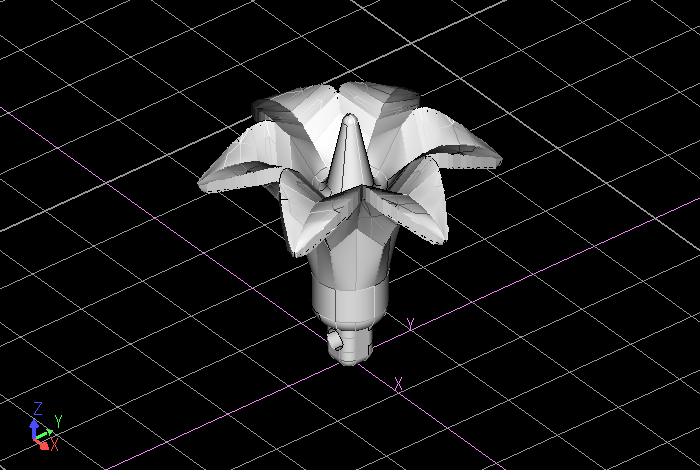
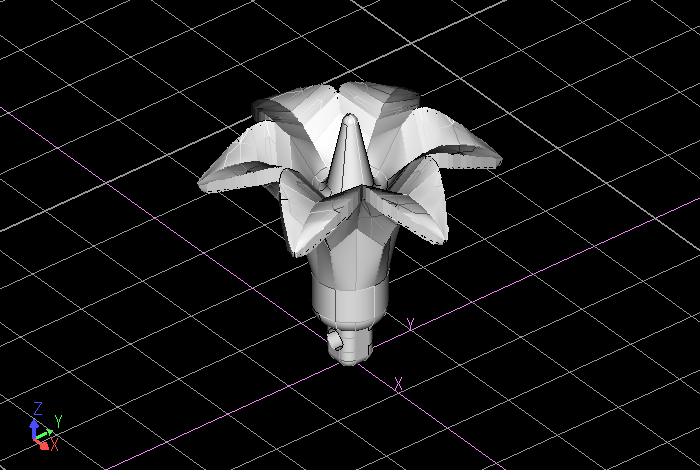 |
シェーディング | 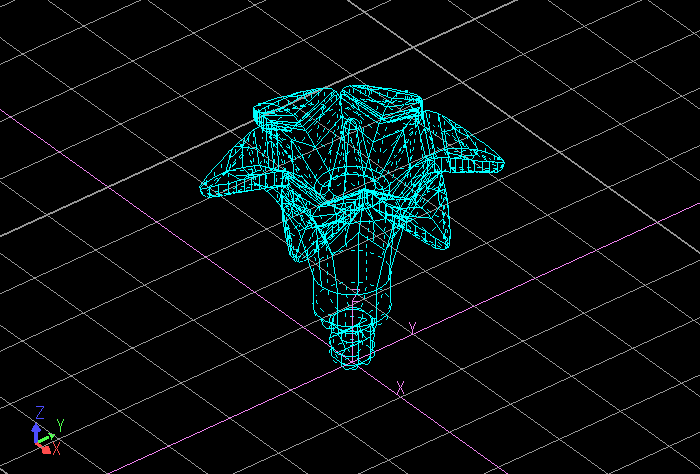 |
ワイヤーフレーム |
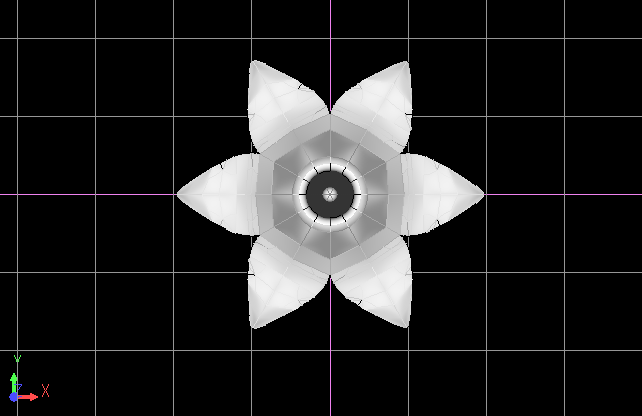 |
上面図 | ||
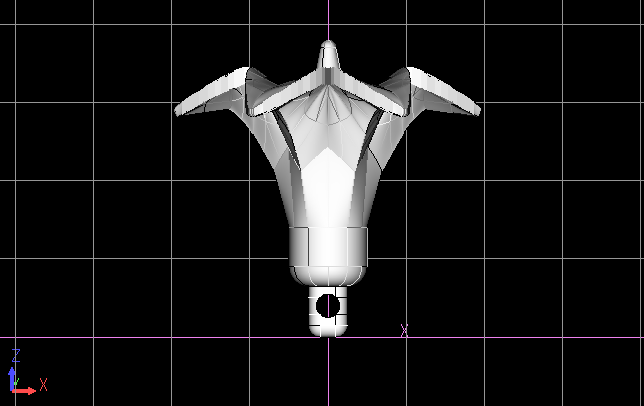 |
正面図 | 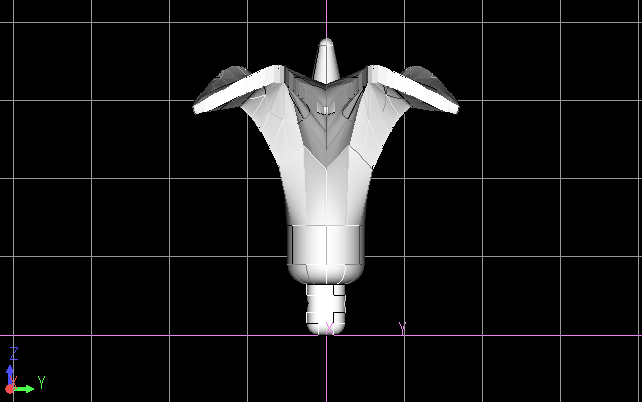 |
側面図 |
| 旋盤での面出し |
| ↓↓ |
| 円柱の直径の調整 |
| ↓↓ |
| 円柱の面取り |
| ↓↓ |
| ノコ盤での切断 |
| ↓↓ |
| 完成 |
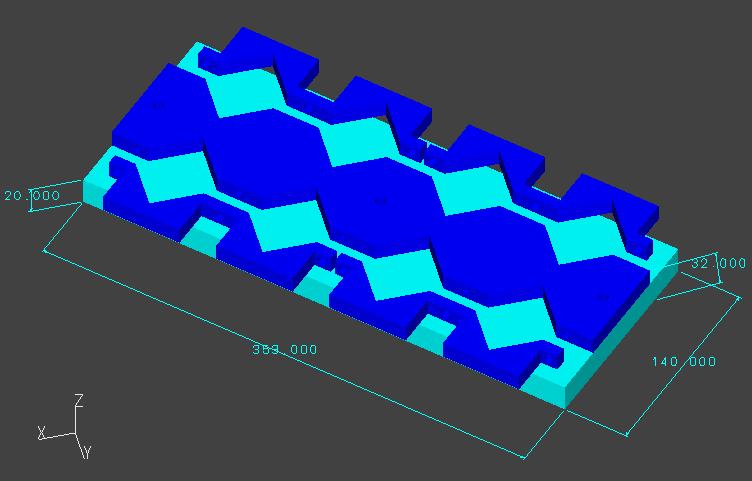 |
全体図 | 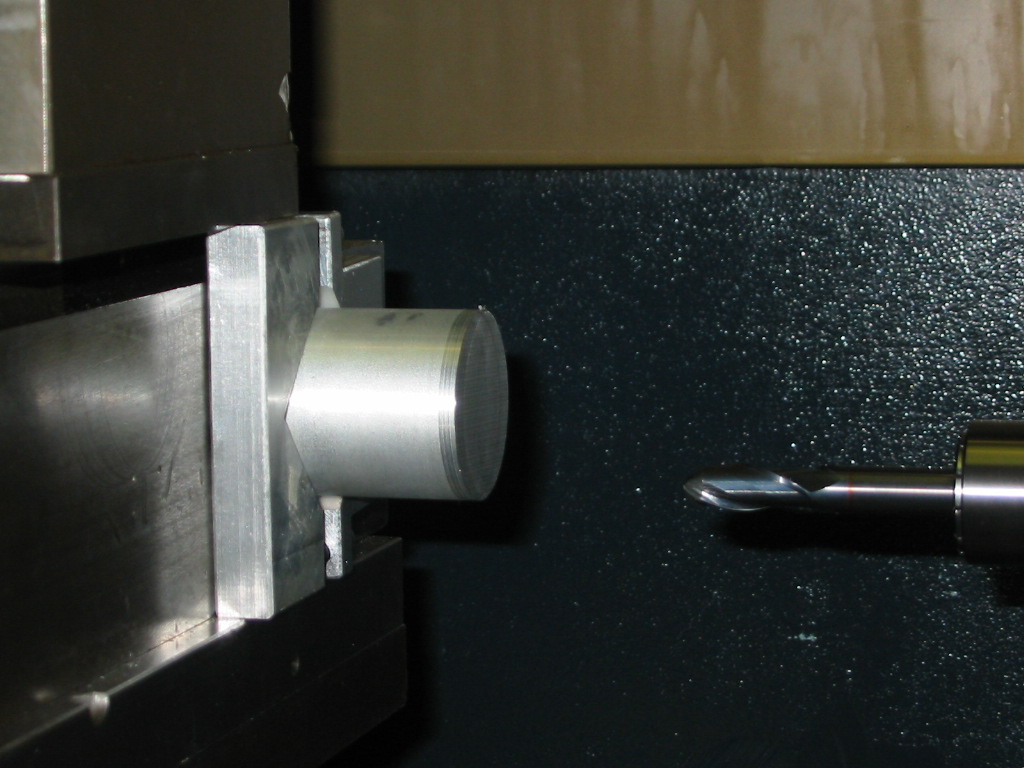 |
試作 |
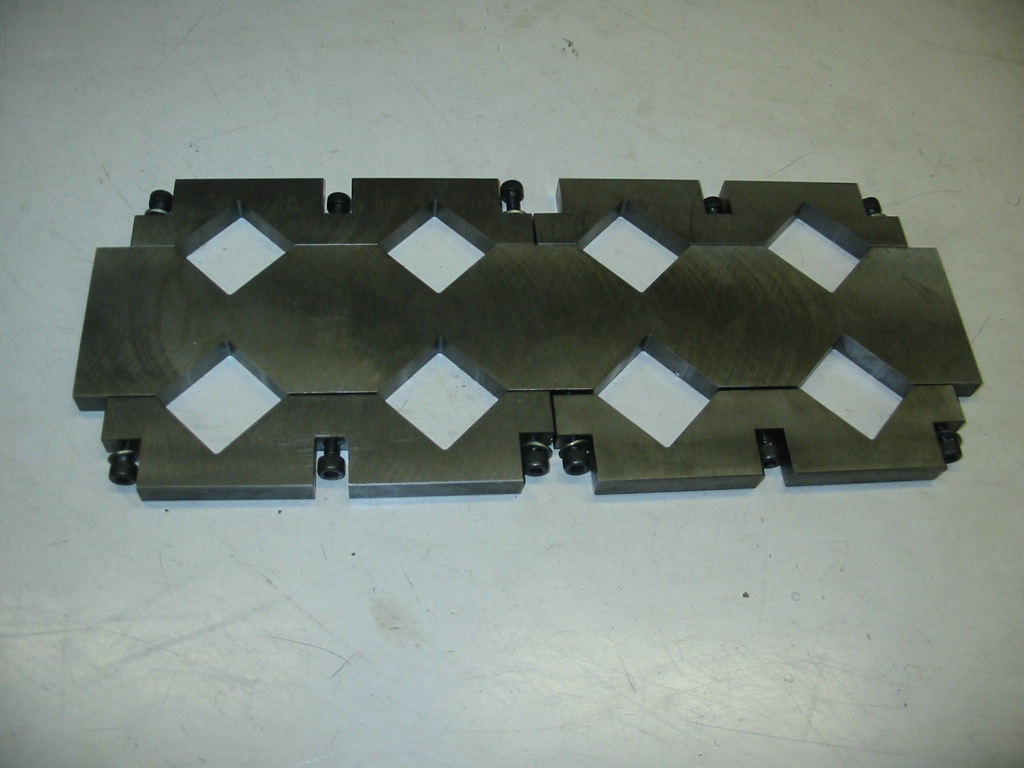 |
完成図 |
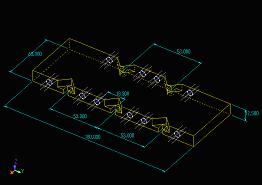 |
全体図 | 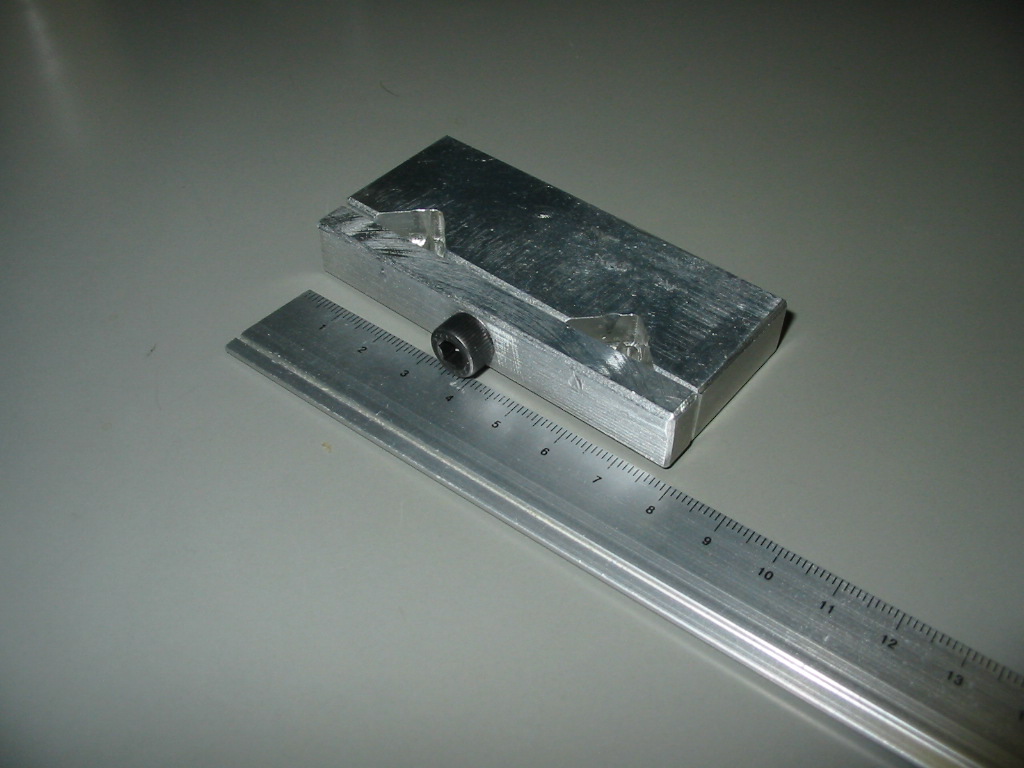 |
試作 |
 |
完成形 |
 |
試作 |
 |
ボールエンドミル |
 |
裏側(1回目) |  |
表側 |
 |
工具干渉部 |  |
裏側(2回目) |
プログラム開始 |
||
ユリを削るデータ | ||
|
||
ユリを削るデータ |
||
|
||
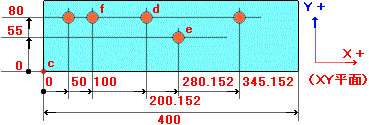 |
図−3 |
| プログラム例 | |
| N001 G90 X280.152Y55 | (G92で変更前の移動指令) |
| N002 G92 X80.Y-25 | (G92で新座標設定) ※この場合変更前のX200.152Y80.に0点が設定される. |
| N003 X-100.152 Y0 | (新ワーク座標系での移動命令になり移動結果として主軸はfに移動する) |